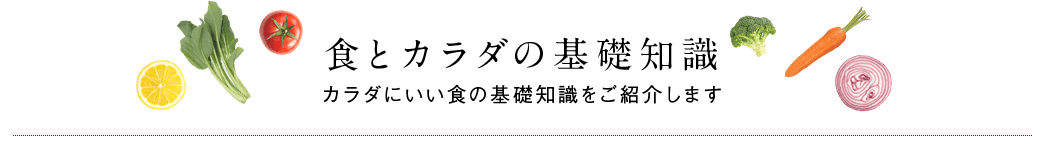
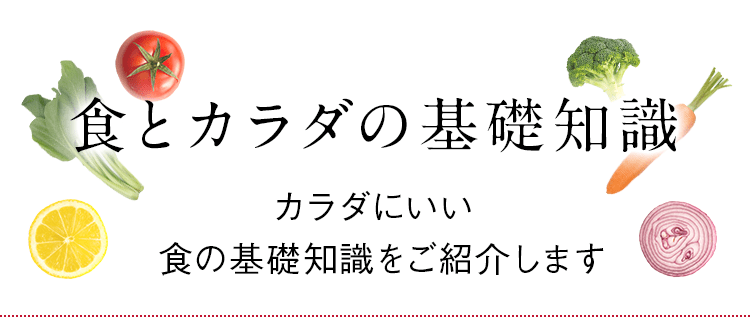
タンパク質は、筋肉を作るために摂取すべきエネルギー産生栄養素の1つです。タンパク質が多い食材を食事に取り入れることで、理想のボディラインを目指すことができます。効率よく体を鍛えるためには、タンパク質を摂取する重要性や1日に必要な摂取量について知っておくことが大切です。
当記事では「タンパク質が筋トレ効果を高める理由」と「タンパク質が多く含まれる食材」について解説します。手軽にタンパク質を摂取できる簡単なレシピも紹介するため、ぜひ作ってみてください。

目次
タンパク質は、人間の体を作るために欠かせない栄養素です。摂取されたタンパク質は、筋肉・骨・血液を作るために使われます。
筋肉は激しい運動により分解され、タンパク質を吸収することで筋肉量の維持と強化を行うことが特徴です。タンパク質が不足すると「肌のうるおい不足」「髪の毛のパサつき」「免疫力の低下」を招きやすくなるため、スポーツ・筋トレ後は積極的にタンパク質を摂取しましょう。
ここからは、タンパク質とタンパク質の種類について簡単に紹介します。
タンパク質は、アミノ酸という単位が連なってできた大きな分子であり、体の中で多様な役割を果たしています。
タンパク質の働きは多岐にわたりますが、その中でも特に重要なのは、酵素としての機能です。酵素は、体内の化学反応を助けるための触媒として働き、人間の生命活動を支えるさまざまな反応をスムーズに進行させます。たとえば、食べ物から摂取した栄養素をエネルギーに変える過程や、新しい細胞の生成など、日常の生命活動に関わる多くの反応に、酵素としてのタンパク質が関与しています。
また、タンパク質は筋肉の構成要素としても知られています。人間が動くためには、筋肉が収縮する必要があり、この筋肉の収縮を担うのもタンパク質です。さらに、免疫応答に関与する抗体や、酸素を運ぶヘモグロビン、体の構造を支えるコラーゲンなども、タンパク質によって形成されています。
タンパク質は、大きく「動物性タンパク質」と「植物性タンパク質」の2つに分類されます。
・動物性タンパク質
動物性タンパク質は、肉、魚、鶏、卵、乳製品など、動物由来の食品から得られるタンパク質を指します。動物性タンパク質の特徴として、人間の体に必要な9種類の必須アミノ酸をバランスよく含んでいる点が挙げられます。
・植物性タンパク質
植物性タンパク質は、豆類(大豆、レンズ豆、ひよこ豆など)、穀物(米、麦、とうもろこし)、ナッツなど、植物由来の食品から得られるタンパク質のことです。植物性タンパク質の特徴として、一部の食品では特定の必須アミノ酸が不足していることが挙げられます。異なる植物性タンパク質源を組み合わせることで、必須アミノ酸のバランスを補完しやすくなります。
野菜類・いも及びでん粉類は、食物繊維やビタミン類が豊富です。一方で、タンパク質含有量は少ない傾向にあります。タンパク質を多く含む主な食材は、下記の5つです。
これらの食材は、アミノ酸スコア(タンパク質量と必須アミノ酸のバランスを示す数値)が高く、健康維持や筋力アップ効果が期待できます。
18~64歳で身体活動レベルが普通の人のタンパク質推奨摂取量は、下記の通りです。
| 1日あたりのタンパク質の推奨量(男性) | ||
|---|---|---|
| 18~29歳 | 30~49歳 | 50~64歳 |
| 86~133g/日 | 88~135g/日 | 91~130g/日 |
| 1日あたりのタンパク質の推奨量(女性) | ||
|---|---|---|
| 18~29歳 | 30~49歳 | 50~64歳 |
| 65~100g/日 | 67~103g/日 | 68~98g/日 |
出典:厚生労働省「「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書」
タンパク質の必要量は、年齢や身体活動レベルによって異なります。身体活動レベルが高い人が健康と美容を維持するためには、身体レベルが低い人よりも多くのタンパク質が必要です。
ここからは、食品分類別にタンパク質が多い食材について解説します。なお、タンパク質量は、文部科学省の「日本食品標準成分表」を参考にしています。
肉類のタンパク質含有量は、下記の通りです。
| 食材 | 可食部100gあたりのタンパク質量 |
|---|---|
| 鶏むね肉(皮なし・生) | 24.4g |
| 豚ロース肉(赤肉・生) | 22.7g |
| 牛もも肉(赤肉・生) | 21.3g |
鶏肉は、皮があると脂質量が多くタンパク質が少なくなります。摂取カロリーを抑えたい場合は、皮なしの鶏肉を選びましょう。豚肉・牛肉は、脂身がない部位を選ぶことがポイントです。
肉類には、赤血球を作り出す「鉄分」、炭水化物の代謝に必要な「ビタミン類」、タンパク質の吸収に必要な「ミネラル」も豊富に含まれています。
魚介類のタンパク質含有量は、下記の通りです。
| 食材 | 可食部100gあたりのタンパク質量 |
|---|---|
| くろまぐろ(赤身) | 26.4g |
| しろさけ(生) | 22.3g |
| あまえび(生) | 19.8g |
魚介類には、肉類と同じように豊富なタンパク質が含まれています。肉類に比べて筋の部分が少ないため、消化しやすいことが特徴です。魚介類を食べると、タンパク質だけでなく「不飽和脂肪酸(DHA・EPA)」などの栄養素も一緒に摂取できます。
卵類のタンパク質含有量は、下記の通りです。
| 食材 | 可食部100gあたりのタンパク質量 |
|---|---|
| 鶏卵(生) | 12.3g |
| ピータン | 13.7g |
| うずら卵(生) | 12.6g |
卵は「食物繊維」「ビタミンC」以外の栄養素をすべて含むことから、完全栄養食と呼ばれるほど栄養価に優れています。また、肉類に比べて脂肪量が低い食材です。卵黄には「ビタミンA」「ビタミンE」が多く、卵白には「ビタミンB2」「カルシウムが豊富に含まれています。
乳製品のタンパク質含有量は、下記の通りです。
| 食材 | 可食部100gあたりのタンパク質量 |
|---|---|
| 普通牛乳 | 3.3g |
| ヨーグルト(低脂肪無糖) | 3.7g |
| プロセスチーズ | 22.7g |
牛乳のタンパク質には、カルシウムの吸収を助ける「カゼインホスホペプチド」や鉄分の吸収を調節する「ラクトフェリン」も含まれています。牛乳が苦手な人は、ヨーグルトやチーズなどの乳製品を食事に取り入れながら、良質なタンパク質を摂取しましょう。
豆類のタンパク質含有量は、下記の通りです。
| 食材 | 可食部100gあたりのタンパク質量 |
|---|---|
| 大豆(全粒・国産・黄大豆・乾) | 33.8g |
| 木綿豆腐 | 6.6g |
| 納豆(糸引き納豆) | 16.5g |
「畑の肉」と呼ばれる大豆には、タンパク質が豊富に含まれています。また、タンパク質のほかに「食物繊維」「ビタミンB群」「ビタミンK」「カリウム」などの栄養素も豊富です。
ただし、豆類に含まれる植物性タンパク質は、肉類や魚介類に含まれる動物性タンパク質に比べて体内への吸収率がやや劣ります。植物性タンパク質だけに頼らず、動物性タンパク質もバランスよく摂取することが大切です。
タンパク質の不足は、体にさまざまな悪影響を及ぼしかねません。タンパク質の不足が筋肉量の減少を引き起こし、その結果基礎代謝の低下や、肩こり・腰痛などを引き起こす恐れがあります。
以下では、タンパク質が不足した際の諸リスクについて紹介します。
筋肉は、人間の体の主要な代謝組織です。タンパク質が不足すると、体は必要なアミノ酸を確保するために筋肉組織を分解します。筋肉の分解によって、筋肉量が減少するので、筋肉量が減少すると基礎代謝も低下します。
基礎代謝とは、安静時(活動していない状態)で消費するエネルギーのことを指します。これには心臓の鼓動や呼吸、体温の維持などの生命維持活動に必要なエネルギーが含まれます。
筋肉はこのエネルギー消費の大部分を占めており、筋肉量が多いほど安静時のエネルギー消費も増加します。そのため、筋肉量が減少すると、それに伴い基礎代謝も低下し、エネルギー消費が減少します。
抗体や多くの免疫細胞がタンパク質から形成されているため、タンパク質が不足すると、これらの抗体や免疫細胞の生成が十分に行われなくなります。
抗体は、体を侵入する病原体や異物に対して特異的に反応し、それらを中和または排除する役割を持っています。抗体が不足すると、病原体に対する防御機能が低下し、感染症にかかりやすくなるため注意してください。
また、免疫細胞には、病原体を直接攻撃する細胞や、免疫応答を調節する細胞など、さまざまな役割を持つものがあります。免疫細胞の機能や数が低下すると、体の免疫バランスが崩れ、病原体に対する防御だけでなく、アレルギー反応や自己免疫疾患のリスクが増加する恐れがあります。
タンパク質は、筋肉や結合組織の形成に必要な栄養素です。筋肉や結合組織は、体を支え、関節や骨を適切な位置に保持する役割を果たしています。タンパク質が不足すると、筋肉の修復や再生が十分に行われなくなり、筋肉の疲労や筋力の低下が生じる恐れがあるでしょう。
筋肉が疲労していると、正しい姿勢を維持するのが難しくなります。特に長時間座った状態や立っている状態では、筋肉のバランスが崩れやすくなるでしょう。このような状態が続くと、筋肉のバランスの崩れから、特定の筋肉に過度な負荷がかかることがあります。たとえば、背中や首の筋肉が疲労していると、肩こりの原因となることが多いです。同様に、腰周りの筋肉が弱っていると、腰痛のリスクが高まります。
さらに、タンパク質はコラーゲンやエラスチンといった結合組織の成分の合成にも関与する化合物です。結合組織が弱くなると、関節や筋肉のサポートが不十分となり、痛みや不調の原因となることがあります。
爪、髪、肌は、ケラチンというタンパク質から主に構成されています。タンパク質が不足すると、ケラチンの生成が十分に行われなくなるため、以下のようなリスクが考えられます。
タンパク質の不足はコラーゲンやエラスチンの生成に影響を及ぼす可能性があります。コラーゲンやエラスチンは、肌の弾力やハリを保つために重要です。
このように、タンパク質は爪、髪、肌の健康を維持するためにも不可欠な栄養素です。
タンパク質を過剰摂取した場合の体への影響として、一般的な健康な成人が短期間に高タンパクの食事を摂取しただけでは大きな問題が発生するわけではありません。しかし、長期間にわたる過剰摂取や、特定の健康状態を持つ人が高タンパクの食事を摂取する場合には注意が必要です。
たとえば、タンパク質の分解過程で生成される尿素などの廃棄物は、腎臓を通じて排出されます。過剰なタンパク質摂取は腎臓に負担をかける可能性があり、特に腎疾患を持つ人は注意が必要です。
またタンパク質に偏った食事は、ほかの重要な栄養素の摂取が不足するリスクがあります。例えば、炭水化物や脂質、ビタミンやミネラルなどの摂取が不足すると、体の機能や健康に悪影響を及ぼす恐れがあります。
厚生労働省が示す「日本人の食事摂取基準」に基づき、さまざまな食品をバランスよく摂取することが大切です。
タンパク質には「吸収率」という、摂取したタンパク質がどれだけ体に吸収され利用されるかを示す指標があります。タンパク質の吸収率は、そのタンパク質のアミノ酸組成、食品の加工方法、他の食材や栄養素との組み合わせ、個人の消化機能などによって変動します。
たとえば、動物性のタンパク質(肉、魚、卵、乳製品など)は、人間の体に必要なアミノ酸をバランスよく含んでいるため、一般的に高い吸収率を持っています。特に、鶏の胸肉や卵、魚は高い吸収率を持つとされています。
一方で、植物性のタンパク質は、一部の必須アミノ酸が不足していることが多いため、動物性タンパク質に比べて吸収率が低い傾向です。
以下は、タンパク質と一緒に摂取したい栄養素をまとめた一覧表です。
| 栄養素 | 栄養素の概要 | 主な食材・食品 |
|---|---|---|
| ビタミンB1 | ビタミンB1は、アミノ酸(タンパク質の構成要素)の代謝に関与しています。特に、アミノ酸の分解やエネルギーの生成に必要な酵素の働きをサポートしています。また、神経機能の正常な維持にも関与しています。 | 豚肉・全粒穀物(玄米など) 落花生・カリフラワーなど |
| ビタミンB2 | ビタミンB2は、タンパク質、脂質、炭水化物の代謝に関与する酵素の成分として働きます。皮膚や粘膜の健康維持にも役立ちます。 | 牛乳や乳製品(ヨーグルト、チーズなど)・卵・ 緑の葉野菜(ほうれん草など)・レバーなど |
| ビタミンB6 | ビタミンB6は、アミノ酸の代謝に深く関与しており、特に非必須アミノ酸の合成や分解に必要です。また、タンパク質の摂取量が増えると、ビタミンB6の必要量も増加すると言われています。ヘモグロビンの生成や神経伝達物質の合成にも関与します。 | バナナ・カツオ・アボカド・鶏肉など |
| ビタミンC | ビタミンCは、コラーゲンというタンパク質の合成に必要です。コラーゲンは皮膚や関節、血管などの組織を形成する主要な成分です。抗酸化作用があり、免疫機能のサポートや鉄の吸収を助ける役割も持っています。 | 柑橘類(オレンジ、レモン、グレープフルーツなど)・キウイ・いちご・ピーマンなど |
| ビタミンD | タンパク質との直接的な関連は少ないですが、ビタミンDはカルシウムやリンの吸収を助けることで、筋肉(タンパク質の一部)の正常な機能をサポートします。主に骨の健康維持や免疫機能の調整にも関与します。 | さけやいわしのような脂質の多い魚・シイタケやマイタケなどのキノコ類(太陽光を浴びたもの) |
| 糖質 | 糖質は主要なエネルギー源として働きます。糖質が不足すると、体はタンパク質をエネルギー源として利用し始めるため、筋肉の分解が進む可能性があります。糖質を適量摂取することで、タンパク質が筋肉の構築や修復に使われます。 | ご飯やパン・パスタ・じゃがいも・果物(特にバナナ、ぶどう、リンゴなど) |
日常の食事を通じてバランスよくタンパク質やそのほかの栄養素を摂取することで、健康や筋肉の維持・増強に寄与します。
タンパク質が含まれる食材はさまざまにあります。無理なくタンパク質を摂取するためには、食材をうまく組み合わせることがポイントです。手軽に作れるメニューを参考にしながら、効率よくタンパク質を摂取しましょう。
ここでは、タンパク質が多い食材を使った簡単メニューを3つ紹介します。
味が淡白なささみは、コクがあるチーズとの相性が抜群です。
【1人前の食材・調味料】
【作り方】
| (1) | ささみを2~3等分に斜めに切り、「」を加えて揉み込む 大葉を千切りにする |
|---|---|
| (2) | サラダ油を熱したフライパン(中火)で、ささみを両面焼く |
| (3) | 中に火が通り両面に焼き色がついたら、細かく切った大葉とパルメザンチーズを入れて混ぜ合わせる |
ささみはしっかり火が通るように、同じ厚みで切りましょう。
卵料理のレパートリーを増やしたい場合は、明太子とチーズを組み合わせたふわふわチーズスフレオムレツがおすすめです。
【1人前の食材・調味料】
【作り方】
| (1) | 明太子・マヨネーズ・牛乳を混ぜてソースを作る |
|---|---|
| (2) | ボウルに卵黄・牛乳・塩こしょうを入れて混ぜ合わせる 卵白はツノが立つまでミキサーで混ぜる |
| (3) | (2)の2つをふんわりと混ぜる バターを熱したフライパン(中火)に流し入れ、弱火にして2分焼く |
| (4) | (3)の上半分にスライスチーズをのせて、半分に折りたたむ 蓋をして弱火で3分焼き、オムレツを器に取り出す (1)のソースをかける |
作業をスムーズに進めるために、卵黄と卵白をあらかじめ分けておきましょう。
動物性タンパク質・植物性タンパク質を一緒に摂取したい人には、豆腐と牛肉のキムチ炒めがおすすめです。
【1人前の食材・調味料】
【作り方】
| (1) | 木綿豆腐をキッチンペーパーで包み、600Wの電子レンジで1分加熱し、一口大にちぎる 牛肉を食べやすい大きさに切り、「○」を揉み込む 長ネギを1cm幅に切る |
|---|---|
| (2) | ゴマ油を熱したフライパンで(1)の牛肉を炒める 牛肉の色が変わったら1cm幅に切った長ネギを加えてさらに炒める |
| (3) | 牛肉に火が通ったら、木綿豆腐・キムチ・「●」を加えて炒める 器に盛りつけたら小口切りにした万能ねぎを散らす |
辛味が苦手な人は、キムチの量を調整しましょう。
タンパク質は、体を作るために必要な栄養素です。タンパク質が不足すると、筋肉量の維持や強化ができないだけでなく、肌のうるおい不足や免疫力低下の原因となります。
体に必要なタンパク質量を十分に摂取するためには、肉類・魚介類・卵類・乳製品類・豆類などのタンパク源をバランスよく食生活に取り入れることがポイントです。食材をうまく組み合わせることで、無理なくタンパク質を摂取できます。手軽にできる簡単メニューを参考にしながら、手軽においしくタンパク質を摂取しましょう。